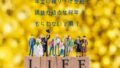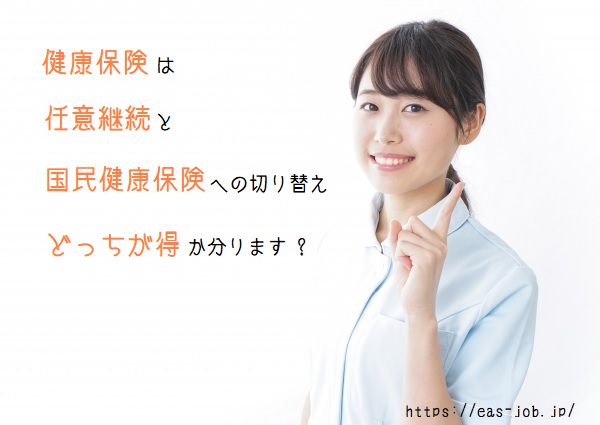
退職したら健康保険はどうしたら良いでしょう ?
選択肢は3つあります。
・現在の健康保険の任意継続を申請する
・国民健康保険に切り替える
・働いている家族の扶養に入れてもらう
家族の扶養に入れてもらえれば自分で健康保険料を払う必要はありませんから楽ですね。
退職後家族の扶養に入る条件に付いてはこちらにまとめてありますのでご参照ください。
退職後 扶養に入る条件とは~年金や失業保険もらったらダメ?
ここでは家族の扶養に入れない方を対象として健康保険の任意継続と国民健康保険への切り替えのどっちが有利かについて徹底的に解説してゆきます。
なお、ここでは国民健康保険との比較は、健康保険として代表的な協会けんぽを例にしていることをお断りしておきますね。
健康保険の任意継続と国民健康保険どっちが得か比較してみよう
健康保険の任意継続と国民健康保険どっちが得か次の7項目を確認した上で比較してゆきます。
・加入条件
・加入期限
・脱退条件
・手続き場所
・手続き書類
・保険料
・傷病手当金・出産手当金
ここでは家族の扶養に入れない方を対象として健康保険の任意継続と国民健康保険への切り替えのどっちが有利かについて徹底的に解説してゆきます。
任意継続が得な人、国民健康保険が得な人
初めに結論を言います。
「任意継続がお得な可能性の高い人」と「国民健康保険がお得な可能性の高い人」は次の通りです。
・扶養家族がいる人
・傷病手当金や出産手当金をうけている人
・独立して収入が上がる可能性が高い人
・倒産・解雇などで退職した人
・退職して収入が減少した人
理由はこれから明らかにしてゆきます。
なお、ここでは国民健康保険との比較は、健康保険として代表的な協会けんぽを例にしていることをお断りしておきますね。
任意継続と国民健康保険の比較表
健康保険の任意継続と国民健康保険はどう違うのか、初めに比較表をお見せしましょう。
国民健康保険と任意継続の比較
| 国民健康保険 | 任意継続 | |
| 加入条件 | 他の健康保険に加入していない | ・社会保険の加入期間が2ヵ月以上 ・退職の翌日から20日以内の申請 |
| 加入期限 | 期限なし | 2年間 |
| 脱退条件 | 他の健康保険に加入したとき | ・加入後2年が経過したとき ・保険料を滞納したとき ・就職して他の健康保険に加入したとき ・本人が申し出たとき |
| 手続き場所 | 各市区町村役場 | 協会けんぽ各都道府県支部 |
| 手続き書類 | 社会保険の資格喪失証明書 | 任意継続被保険者資格取得申出書 |
| 保険料 | 市区町村により異なる 前年度の収入で決まる |
都道府県により料率が異なる 任意継続前の2倍(上限あり) 原則任意継続中は変わらない |
| 扶養者の扱い | なし | 扶養者も継続対象となる |
| 傷病手当金 出産手当金 |
なし | 条件を満たせば受給可 |
違いのポイントは次の5つです。
・健康保険の任意継続には扶養の概念があるが国民健康保険にはない
・健康保険の任意継続は保険料が退職前の2倍
・任意継続は条件を満たせば傷病手当金や出産手当金をもらえる
・倒産・解雇などで退職した場合は、国民健康保険に優遇措置あり
・退職して収入が減少すれば翌年度は国民健康保険料は安くなる
順にご説明しましょう。
扶養者の扱い
協会けんぽなどの健康保険には「扶養」の概念があって、本人が保険料を払うことによって被扶養者は保険料を払わずに保険の適用を受けることができます。
これは任意継続をした後も変わりません。
一方国民健康保険には「扶養」の概念はありませんから、国民健康保険に切り替えれば家族の人数分保険料を払う必要が生じます。
ですから、扶養家族がいる人はほとんどの場合任意継続した方が「お得」と言えるでしょう。
一方扶養家族がいない人は国民健康保険の方が安くなることがあります。
市区町村の保険課に国民健康保険に切り替えた場合の保険料を問い合わせることがてきます。
その際、源泉徴収票や確定申告書など、前年中の所得が確認できるものを用意しておく必要があります。
扶養家族がいる人は扶養家族全員の分も必要ですよ。
任意継続は保険料が退職前の2倍
会社勤めをしている人や公務員の保険料は、本人と会社または国・都道府県が折半となります。
つまり本来の保険料の半分を払えばよいのです。
ところが退職すると全額自分で払わなくてはなりません。
そのため、保険料は退職前の2倍になるのです。
ただし、任意継続の保険料には上限があります。
上限は標準報酬月額30万円の保険料
となります。
これは2022年(令和4年)現在で、毎年被保険者の平均によって見直しがなされています。
「標準報酬月額」というのは、給料の等級のようなもので、月額58,000円~1,390,000円まで50段階が設定されています。
この等級ごとに健康保険料、介護保険料、そして厚生年金保険料が定められているのです。
そして保険料は都道府県ごとに微妙に異なっています。
参考
東京都の標準報酬月額表
では任意継続の上限である2022年(令和4年)現在の標準報酬月額30万円の保険料はいくらかと言いますと、たとえば東京都では
健康保険料が14,715円×2 = 29,430円、介護保険料が2,460×2 = 4,920円です。
任意継続は条件を満たせば傷病手当金や出産手当金をもらえる
協会けんぽや企業の健康保険組合などには「傷病手当金」の制度があります。
これは、病気やケガで連続する3日間を含む4日以上休職して、その間給料や手当が支給されなかったときに、健康保険から支給される手当です。
支給額は標準報酬日額の3分の2が支払われます。
金額や期間についてはこちらに詳しくまとめてありますよ。
標準報酬日額とは何かもこちらをご参照ください。
傷病手当金は退職してももらえる ? 遡っての申請はできるか ?
任意継続に移行してから病気やケガになった場合は「傷病手当金」は支給されませんが、任意継続に移行する前、つまり退職前に病気やケガになって傷病手当金の支給を受けていた場合は本来受けることができるはずであった期間は継続して給付を受けることができます。
これは、健康保険法第104条によって定められているのです。
一方、傷病手当金の制度は国民健康保険にはありません。
同様に出産手当金も退職前から受けている場合は本来の受給期間の間受け続けることができます。
出産手当金を受けられる期間
基本は、出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間
支給される金額
傷病手当金と同じく標準報酬日額の3分の2が支払われます。
参照 : 協会けんぽ
出産に関する給付
倒産・解雇などで退職した場合は、国民健康保険が有利の可能性あり
倒産・解雇など会社の都合で退職した場合は、国民健康保険料の軽減措置が適用されます。
これは、失業から一定期間、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料を計算することで、国民健康保険料を安くすると言う制度です。
国民健康保険料は前年度の収入を基準として計算されるので、効果が出るわけです。
ちなみに軽減措置が適用されるのは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下の表に該当する方です。
| 離職理由コード | 備 考 | ||||||
| 特定受給資格者 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 会社の倒産、解雇などで離職 |
| 特定理由離職者 | 23 | 33 | 34 | 雇い止めもしくは正当な理由のある自己都合(※)などで離職 | |||
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力、聴力、触覚の減退による離職
②妊娠、出産、育児により離職し、雇用保険の受給延長措置を受けた場合
③父母の死亡、疾病、負傷又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病等による離職
④配偶者や扶養親族と別居を続けることが困難となった場合
⑤次の特定理由により通勤が困難となった場合
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育園等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意に反する住所移転
・鉄道、軌道、バス、その他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
なお、自己都合(離職コード40)で退職された方は、国保の軽減制度の対象にはなりません。
また、特定受給資格者や特定理由離職者は失業保険でも優遇されますよ。
失業保険についてもっと知りたい方はこちらをどうぞ。
失業保険をもらえる条件とは ? もらえないこともある !!
裏技-はじめ任意継続として収入減なら1年後に国保に切り替える
扶養家族がいて任意継続の方が保険料が安い場合は迷わず任意継続とします。
でも、退職して例えば年金生活となった場合、1年後は年収が大きく減少していることが予想されます。
その場合は任意継続は1年(注)でやめて国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる可能性が高いです。
任意継続は2年が保険料が変わりません。
一方、国民健康保険の保険料は前年度の収入で変わるからです。
任意継続で1年経過したら、国民健康保険料を市区町村の保険課で試算してもらってみてください。
安くなるのなら1年でも早く切り替えた方が「得」です。
注 :
以前は任意継続の期間は2年間と決まっていて途中でやめることができませんでした。
しかし2022年4月1日以降は、2年以内でも本人の申し出によって脱退が可能となりました。
一度国民健康保険に加入してしまうと任意継続はできなくなりますので要注意です。
任意継続の加入期限は退職日の翌日から20日以内だからです。
独立して収入増なら任意継続が得の可能性あり
独立して収入が増加するなら任意継続の方が保険料が安い可能性があります。
理由は国民健康保険は前年度の収入で保険料が決まるため、収入が増えれば1年後に保険料が高くなるからです。
一方の任意継続は、退職時の保険料の2倍にはなりますが、継続期間中は保険料が上がることはありません。
おわりに
いかがでしたか ?
退職したときに、健康保険の任意継続と国民健康保険への切り替えではどっちが得かお伝えしてきましたが、参考になりましたでしょうか ?
最後にもう一度まとめておきますね。
次の人は任意継続がお得になる可能性が高い
・扶養家族がいる人
・傷病手当金や出産手当金をうけている人
・独立などで退職前より収入が増える人
次の人は国民健康保険がお得になる可能性が高い
・倒産・解雇などで退職した場合は、国民健康保険が有利の可能性あり
・退職して収入が減少した人
保険料は自分で試算するより、とりあえず任意継続してから、市区町村の保険課で国民健康保険の額を試算してもらってから決めれば良いですよ。
最後までお読みくださってありがとうございました。